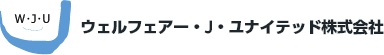やっぱり、なんちゃって急性期は、滅びますかね。当然と言えば当然ですが、もう、機能がないのに急性期と言い張って経営していると、倒産するリスクが大幅に増す感じでしょうか。
また、私が注目しているのは、「高齢者の退院からのフロー」と、「フローから看取りまでのプロセスごとの事業の配置」とその「収支」です。すごく分かりやすく言うと、退院後の在宅医療、訪問看護、訪問介護、住まい、生活支援、そして、再度の入院・退院、在宅医療、訪問看護、訪問介護、住まい、生活支援のサイクル(数回)、そして、看取りに向けた介護保険事業、そして人生の卒業までのサポートです。
私は、できれば、この「高齢者の退院からのフロー」と、「フローから看取りまでのプロセスごとの事業の配置」とその「収支」を社会福祉法人でできないかなと、ずっと、思っているのです。もう、古い考えで頭が化石化している病院の経営者ではなく、若い、街を守ろうとする社会福祉法人の経営者がこれができないか?と。
こんな風に書くと「それは理想だよ。」笑われますかね。でもね、ちゃんとやっているところはあるのです。考えるヒントをいただいたのは、尊敬してやまない、志村フロイデグループの鈴木先生の発想と行動力です。だから、その気になれば、山ほど情報はあるわけで、取りに行く努力をすればいいだけですね。
(記事)
新たな地域医療構想は、病棟・病床の機能に加えて「病院の機能」を報告させて病院の機能に、「手術や救急医療等」の医療資源を多く要する症例を集約化した医療提供を行う「急性期拠点病院機能」が加わるようです。
2026年改定でも重要検討テーマとなり、救急搬送受け入れ件数、全身麻酔手術の実施件数、などの高度急性期医療提供実績が評価指標になると考えられる。
それと、以下の流れが鮮明になって行く感じでしょうか。
だから、退院後の在宅を制したものが地域医療を制する時代が、必ず来る感じです。
(厚労省資料より)
令和6年度診療報酬改定では、後期高齢者の救急搬送の増加等、入院患者の疾患や状態の変化を踏まえて、機能分化・強化を促進し、効果的・効率的な提供体制を整備するとともに、高齢者の中等症急性疾患のニーズ増大に対して地域包括医療病棟が新設された。また、患者が可能な限り早く住み慣れた自宅・施設に復帰できるよう各病棟が果たすべく役割に念頭に評価体 系が見直された。
さらに、介護保険施設等と地域包括ケア病棟を持つ医療機関や在宅療養支援診療所の平時および急変時の対応の強化に関する見直しが実施された。また、患者の望む医療・ケアの提供を推進する観点から、在宅医療分野においてICTを用いた情報連携に関する評価の見直し等が行われた。
2.2040年頃の医療をとりまく状況と課題(抄)
(1) 医療需要等
2040 年の医療需要については、85 歳以上の高齢者は医療・介護の複合ニーズを有する場合が多く、85 歳 以上人口の増加に伴い、2020 年と比較して、85 歳以上の高齢者の救急搬送は 75%増加し、85 歳以上の在 宅医療の需要は62%増加することが見込まれる。また、認知症の人の数は増加している。
高齢者救急については、自宅以外の高齢者施設等からの救急搬送の増加も見込まれるほか、発症後の生活機 能を維持するためのリハビリテーションや、退院後の生活環境等も踏まえた退院調整がさらに重要となる。
医療提供体制の現状と目指すべき方向性(抄)
(1)新たな地域医療構想における基本的な方向性
医療と介護の複合ニーズを抱える 85 歳以上の高齢者の増加や人口減少がさらに進む 2040 年、さらにその 先を見据え、全ての地域・全ての世代の患者が、適切に医療・介護を受けながら生活し、必要に応じて入院し て、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保できる医療提供体制を構築す る必要がある
このため、新たな地域医療構想において、以下の4点を中心として、限りある医療資源を最適 化・効率化しながら、「治す医療」を担う医療機関と「治し支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確化 し、地域完結型の医療・介護提供体制を構築する必要がある。
1点目は、増加する高齢者救急への対応である。高齢者救急について、その受入体制を強化するとともに、 ADLの低下を防止するため、入院早期から必要なリハビリテーションを適切に提供し、早期に自宅等の生活 の場に戻ることができる支援体制を確保することが求められる。その際、救急搬送や状態悪化の減少等が図ら れるよう、医療DXの推進等による在宅医療を提供する医療機関や高齢者施設等と地域の医療機関との連携強 化、かかりつけ医機能の発揮等を通じて、在宅医療を提供する医療機関や高齢者施設等の対応力を強化することも求められる。
新たな地域医療構想(抄)
(3)医療機関機能・病床機能
医療機関機能の名称と定義
高齢者救急・地域急性期機能
高齢者をはじめとした救急搬送を受け入れるとともに、必要に応じて専門病院や施設等と協力・連 携しながら、入院早期からのリハビリテーション・退院調整等を行い、早期の退院につなげ、退院後の リハビリテーション等の提供を確保する。
高齢者をはじめとした救急搬送を受け入れるとともに、必要に応じて専門病院や施設等と協力・連 携しながら、入院早期からのリハビリテーション・退院調整等を行い、早期の退院につなげ、退院後の リハビリテーション等の提供を確保する。※地域の実情に応じた幅をもった報告のあり方を設定
在宅医療等連携機能
地域での在宅医療の実施、他の医療機関や介護施設、訪問看護、訪問介護等と連携した24 時間の対 応や入院対応を行う。※地域の実情に応じた幅をもった報告のあり方を設定 ・ 急性期拠点機能(略)
専門等機能 (略)
※ 高齢者医療においては、あらゆる段階において、マルチモビディティ(多疾病併存状態)患者へのリ ハビリテーションを含む、治し支える医療の観点が重要である。

5月22日に開催された診療報酬調査専門組織「入院・外来医療等の調査・評価分科会」(以下、入院・外来医療分科会)で、こういった議論が行われました。2026年度の次期診療報酬改定に向けて「入院・外来医療改革の議論が本格スタート」しています。調査結果は極めて膨大なため、本稿では「急性期入院医療」に焦点を合わせて、他の項目(DPC、高度急性期入院医療など)については、別稿で報じます。