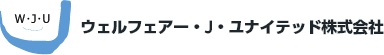私は、沖縄県中部から沖縄の障がい事業のあり方を本気で変えられないか考えています。なんか、このブログを読む方は、「あいつは、障がい事業で大きくしたいだけだろう。」と思っていることと思います。
それは、そうなのですが、もう一つ、私は、沖縄県中部から沖縄の障がい事業のあり方を本気で変えられないか考えています。今日、障がいコンサルタントの赤松さんに「地域の事業者を集めて、研修会を開こう。」と。
先日、このブログでも書きましたが、はぴねす福祉会の長野会長から、障がいの奥行きについて教えていただきました。大変、勉強になり、考えていたことが間違っていなかったのだと。その時に、ジョージ・ルーカス、トム・クルーズも、障がいがあるものの、それを克服して大活躍している話が出てました。私も彼らの障がいの話は知っていましたので、療育が必要な子たちを包み込むように育てる手伝いがしたいと。そのためには、もっと、きめ細かな関わりをするための知識が必要だと。
WJUは、皆生平衡会を立ち上げて、沖縄県の中部地区の障がい事業の中心になることを目指したいと思います。研究・教育を行いたいと。そのためにも、お金が必要なので、30億円の規模にして利益を上げて、人づくり、研究・教育に当てたいと思います。
どんなに大変でも挑戦したいですね。全ては「夢」から始まります。世代を超えてバトンが渡せるようにしたいです。
(以下、「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会より)
障害福祉福祉分野
障害福祉分野における需要については、人口構造だけでなく様々な要素が関係し、精神障害や障害児を中心にサービス利用が伸び続ける一方、中山間地域や小規模自治体においてはサービス の利用に減少傾向が見られる。また、障害種別に応じたきめ細かい対応が必要となる中、提供体制や実施事業、地域資源についても地域差があり、自らが希望する事業所のサービスを利用するために広域的なサービス利用となる場合がある。とりわけ今後、中山間・人口減少地域においてサービス提供体制をいかに維持・確保していくかは、他分野とも共通の課題。
現行制度においては、共生型サービス、基準該当障害福祉サービスや多機能型、従たる事業所など、一定の要件の下で柔軟なサービスの提供を可能としているところであるが、中山間・人口減少地域においても、引き続き障害者が安心して地域生活を送ることができるようにしていく必要がある。
障害福祉分野においても、現行制度の活用状況を確認しつつ、現行制度の効果的な活用を促進 していくべきではないか。また、他制度も参考としつつ、必要に応じ、配置基準の弾力化など、制 度を拡張・見直しをして対応していくことが考えられるか。
分野を超えた総合的な福祉サービスの推進に向けて、これまでも共生型サービスを創設すると ともに、高齢者、障害者、児童等に対して複数の福祉サービスを総合的に提供する上での人員・設備の兼務・共用等が運用上可能な事項についてガイドラインで示すなど、取組を進めてきたところ。
介護、障害福祉、こどもといった分野をこえた福祉サービスの推進に向けて、更に人員・設備の兼務・共用など柔軟対応についてどのような方策が考えられるか。
また、共生型サービスについては、都道府県ごとに取組状況に差も見られるところ、自治体や事業所の取組の更なる推進に向けた方策を検討すべきではないか。