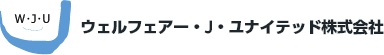だから、このブログでいつも書いている通り「経営する」ことなわけです。
誰がどのようにマネジメント設計図を書いて行うかです。
(記事)
「国立大学病院の約7割が赤字」という危機的な状況に直面している日本。そのなかで異例の黒字経営を続け、10億円超の経常利益を上げた病院がある。広島大学病院だ。
今年7月、国立大学病院の病院長でつくる国立大学病院長会議は、42ある国立大学病院全体の2024年度の経常赤字額が過去最大の285億円に達したと発表した。
医薬品費や診療材料費の上昇などが業績を圧迫し、前年度は20億円超あった経常利益が半分に。それでも踏みとどまっているのは、「経営企画グループが中心になって取り組んでいる経営改善策が実を結んでいるからではないか」
黒字経営を続ける意義について、「黒字を確保することで、医療現場が必要とする最新の医療機器などを購入できたり、医療従事者の処遇改善に資金を回せたりするなど、物や人への投資が可能となる。いろいろと切り詰める必要もない。いい医療を提供することで患者さんが集まり、外部資金が集まるという好循環を生む」と言う。
購入にも維持にも莫大なコストがかかる医療機器の購入にあたっては、2018年度から医療機器ディーラーの元社員2人を購買担当として採用した。医薬品価格の交渉のほか、高額医療機器の購入の際には、1社だけでなく相見積もりを取るよう徹底。
病院経営を圧迫する要因である医師などの医療スタッフの人件費については、コストアップをいとわず、若手医師、特に外科医に対してインセンティブを付与する取り組みを始めた。
同病院の黒字経営の背景には、ウルトラCのような秘策がないことがわかった。診療科ごとの収支チェック、こまかなコスト削減の積み上げが黒字を生んでいた。
文部科学省も同病院に着目し、今年8月にとりまとめた国立大学を健全に運営するための改革の指針に「診療科別の収支分析をさらに推進することで経営効率化を図る」という文言を盛り込んだ。