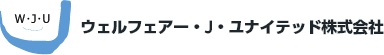ほんと、法人経営と一緒です。
ほんと、法人改革と一緒です。
ほんと、改革派と守旧派の対立、お家騒動なんて、法人の立て直しで怒ること一緒です。
で、「成せばなる、成さねばならぬ何事も、成らぬは人の成さぬなりけり」となります。
【上杉鷹山の藩政改革】
米沢藩、長年の経営者不在の放置。膨大な借金と敗者のメンタティーが支配。
国は疲弊し、民は疲弊し、一部の重役が藩を牛耳り改革派を潰す。
そんな中、、、、
0 上杉鷹山藩主になる
1 藩主による藩政改革宣言
江戸屋敷で改革チーム結成
2 財政改革案作成
3 質素倹約の実行
4 武士が範を示し、殖産振興開始
改革派と守旧派の対立、お家騒動
5 藩が一つにまとまる
勝者のメンタリティー
6 殖産振興による財政再建
7 藩校創設により人づくり開始
8 財政再建
上杉鷹山藩主引退(35歳)
伝国の辞
一、国家は先祖より子孫へ伝え候国家にして我私すべき物にはこれなく候
「国家は先祖から子孫に伝えるところの国家であって、自分で身勝手にしてはならないものです。」
一、人民は国家に属したる人民にして我私すべき物にはこれなく候
「人民は国家に属しているから人民であって、自分勝手にしてはならないものです。」
一、国家人民のために立たる君にし君のために立たる国家人民にはこれなく候
「君主は国家と人民のために立てられているのであって、君主のための国家や人民ではありません。」
9 後見として改革を仕上げる
永眠(72歳)
上杉鷹山(うえすぎ・ようざん)
宝暦元年(1751)7月20日、日向国高鍋藩主秋月種美の二男として江戸で生まれる。10歳のとき、男子のなかった米沢藩主上杉重定の養子となる。14歳から細井平洲より藩主教育を受け熱心に学び、16歳で元服。将軍家治の一字を賜って治憲と名乗る。鷹山というのは後の号。
17歳の明和4年(1767)に家を継ぎ、第9代米沢藩主となる。当時の米沢藩は、家臣団の多さ、幕府御手伝普請、飢饉などで藩財政は困窮し農村も疲弊した状況で、鷹山は「民の父母〈たみのちちはは〉」の気持ちで藩を立て直そうと決意し、大倹約令を布達〈ふたつ〉、自ら率先して倹約に努めるなど、改革に着手。
農業の大切さを示すため自ら田を耕す「籍田の礼」を行なう一方、腹心の竹俣当綱や莅戸善政らは、漆・桑・楮の100万本植立や縮織(ちぢみおり)の導入を図るなど積極的な殖産政策を進める。また、学問が重要と師細井平洲の指導の下で藩校「興譲館」を設立し、人材育成に努める。
旧守派重臣たちによる反対事件が起き、鷹山は多くの家臣の意見を聞いた上で、果断に反対派を処罰し、危機を乗り切る。
天明5年(1785)、35歳で隠居。その際、藩主の心得として養子治広に「伝国の辞」を贈る。同7年 、「国政別格」と幕府から表彰され、老中松平定信は「三百諸侯随一の名君」と讃る。隠居後も藩政を後見、改革は続けられ、養蚕・絹織物が特産物に発展し、農村は興隆、藩財政も好転する。
文政5年(1822)3月12日、米沢で死去、享年72。