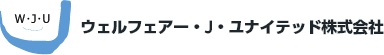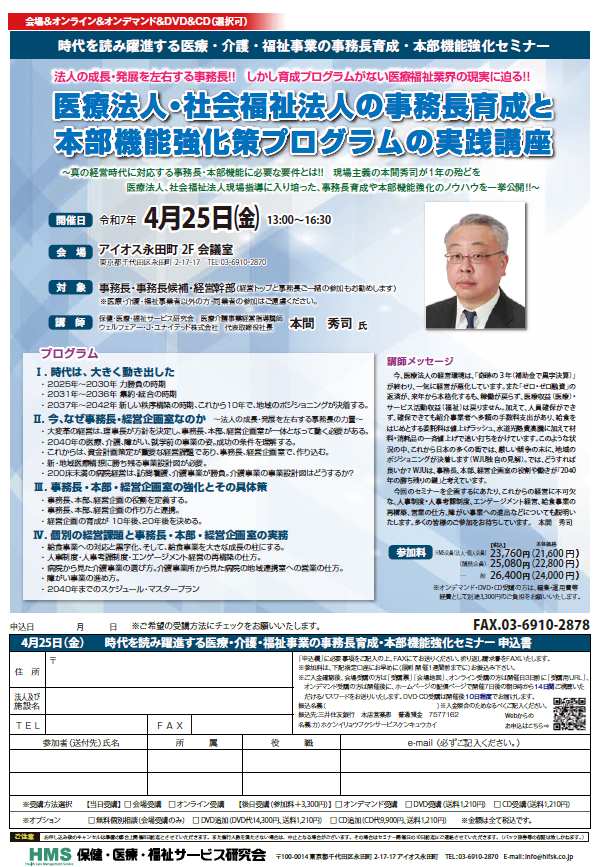700億円を売り上げる企業であっても、「時代」と離れて仕舞えば、厳しい現実が待っています。
1970年モデルは、「時代」合ってますか?
キーワードは「時代」です。
そう、HMSエリートコースに来て下さい。こんな話も聴けますから。
楽しんで、かつ、恐れて、かつ、出口を見つけて帰れますよ。
(記事)
丸住製紙(株)(四国中央市) と、関連2社は2月28日、民事再生法の適用を申請し同日、監督命令を受けた。
1919年7月創業の業歴100年を超える老舗企業。手漉き和紙で創業し、その後新聞用紙など出版・印刷・情報・加工用の様々な洋紙の製造を手掛けてきた。四国中央市内に2カ所の主力工場を設置し、地元を代表する製紙会社として知名度を有し、ピークの2008年11月期には売上高約743億3500万円をあげていた。
しかし、電子書籍やオンラインニュースなどのデジタル媒体の需要が高まる一方、当社が扱う新聞や出版物などの紙媒体の需要減など市場環境の変化から業績は次第に低迷した。そのため2019年以降、ペーパータオルやウエットティッシュなど衛生用品のほか、コスメ分野への新規進出といった新商材への取り扱いを強化した。この間、積極的な設備投資も実施し、2023年4月には約90億円を投じて大江工場に設置した衛生用紙抄紙機および加工設備が稼働していた。
一方で、近年は新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済活動の停滞に加えて原材料、エネルギー価格の高騰なども重なり、多額の損失が発生。2022年11月期は約117億1100万円、翌2023年11月期も約150億円の最終赤字を余儀なくされた。リストラ実施や金融機関からの支援、スポンサー支援などを模索して経営改善を目指した。こうしたなか、2月に入って主力の洋紙事業からの撤退を取引先に通知するなど動向が注目されていた。
(HMSエリート初級編より)
この仕事をしていると、医療法人・社会福祉法人・株式会社のみなさんに、経営を考える題材として何がいいのかを考えます。その時に一番のケーススタディになるのは、富士フィルムという会社です。
パラダイムシフトの中で、生き残るだけではなく、地獄の口が開いた時にそれを土台として飛躍するというマジックのようなことをやってのけた会社です。英雄がいれば引き立て役がいるもので、その役をするのが、フィルムの巨人、イーストマン・コダック社です。世界のシェアを抑えていたコダックは2012年1月に倒産します。10年前までフィルムの世界シェア No.1だった会社が10年で倒産するのです。こんなことが理解できるでしょうか? なぜなら、2001年まで、フィルムのマーケットは、年率 5%程度成長していたからです。では、何が世界N◯.1の会社を滅ぼし、後塵を拝していた富士フィルムが苦境をバネに躍進したのでしょうか? 結論は、経営者の違いであり、社員の違いです。富士フィルムは、まさに劇的に変化するマーケットに、社内を大変革し、フィルム中心の事業を、医療・LCD・半導体・ITの会社に変えたのです。私が一番感銘を受けるのは経営者の強い決意です。
この経営者は、「変化を恐れず、自法人の強みを生かし新しい分野に挑戦する」信じられないほど過酷なマーケットに果敢に挑んだ歴史です。富士フィルムのHPには以下のように書かれています。「写真フィルム国産化を目指してスタートした富士写真フイルムの歴史は『苦悩』と『果敢なチャレンジ』が交錯するスリリングな歴史であった」と。みなさんは、樹木希林と岸本加世子の富士フィルムの宣伝をおぼろげながら覚えていると思います。「写ルンです」です。しかし、今の富士フィルムのテレビ宣伝といえば、医療関係の新製品のCMです。医療・福祉の経営者の方にお伝えしたいのは「医療・介護・障がいの各事業は、大きな大変革期を迎えている」ことです。勝ち残る法人は、気合と根性ではなく、冷静に自法人のドミナントを分析し、変化を恐れず果敢に挑戦することが求められています。
今は、戦国時代の幕開けです。もはや室町幕府に統治する力はありません。戦国大名が地域を支配する時代の始まりです。これからは知恵と勇気とマネジメントが勝負です。そして、戦国時代が終わってしまえばもうチャンスはありません。仙台の伊達政宗をみれば分かります。もし、政宗が20年早く生まれていたら、果たして徳川幕府があったかどうか分からないと言われています。では、もう少し、富士フィルムの変革の歴史をみてみましょう。世の中にデジカメが現れたのは2000年です。今では当たり前にようにスマホで気軽に画像を取り込んでますが、私は初めてデジカメを見たときの驚きを今でも覚えています。それまでは、1時間で写真にしますってお店に写るんですで撮ったフィルムを持ち込んでいたので。さて、デジカメの登場とともにフィルムのマーケットは劇的に縮小します。2000年を100とすると、ほぼ10年で、90%減になったのです。この需要の減少とともに事業が縮小したのです、イーストマン・コダックは。なんと、デジカメを開発したのは当のコダック自身だった。信じられないことに、デジカメの時代が来ると予見しながら、「津波が来るのを目の当たりにして何も打つ手がない状態」と言われるほど何もしていない。あまりの成功体験が変化することを阻んだ。
経営者もコロコロ変わり、会社のことを長いスパンで考える人がいなかった。変わる勇気のある経営者がいたとしたら、結果は違っていたかもしれないですね。しかし、富士フィルムは違いました。まず、富士フィルムは経営者を交代させた。なぜなら、主力のフィルム事業の売上が2,750億円から激減するのは目に見えていたので、新しい価値観が必要となった。結果として、フィルム事業の売上が2,750億円から300億円に10年で激減することになる。
新しい経営者は、社員に対してこう話をした。「車が売れなくなったトヨタ自動車を想像してほしい。」と。この新しい経営者は変化を恐れず、そして大胆だった。社長は40社の買収に90億ドルをつぎ込み、第二創業と呼べるほどの勢いで改革を進め、1年半で2,500億円をかけて社内を大再編した。事業は、2000ものフィルム用化学物質の技術を使って医療、LCD、半導体、ITの会社になることで生き残った。例えば、2000年に売上高280億円(2%)だったLCD用の「タックフィルム」は、2010年には2,300億円(10%)に成長させた。このLCD用フィルムは世界シェア70%を占めているとされている。富士フイルムの成功は、「企業とは変化対応業である。」ということを理解させる。そして、「経営者は決して人のせいにせず、すべての責任を負い、大胆に勝負する。」を貫いた結果といえる。
経営者はかくありたいものです。富士フィルムは、デジカメが市場を席巻し始めた2000年から社内変革を進め、翌年から大幅に売上を伸ばします。ここからの躍進は素晴らしく、コダックが1兆5,000億円から4,000億円に急下降するのとは反対に、2000年1兆円だったものが2010年には2兆3,000億円と2.3倍にするほどでした。経営者でこれだけ変わるのが企業です。多くのビジネススクールでは、コダックの崩壊がケーススタディーで使われます。そこでは、「経営陣が心地良い椅子で居眠りしていた。」と言われています。今、日本はすべての産業が同じような大変革期を経験しているのだと理解しています。① IT、ICT、AI などのイノベーション、② 急激な少子高齢化社会、③ 日本人のライフスタイルの変化。「今は、すべての業界で、変化を求められる経営者の時代です。経営者の方にこんな会社もある、やればできると考えていただければ幸いです。」