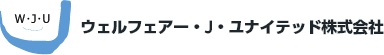居宅+有老+訪問看護 =超高収益のビジネスモデルは、思いっきりやられますね。厚労省は、基本、性善説で制度は設計するわけで、それを運営する事業者は、コンプライアンスが命なわけで。26年・28年・30年の医療改定、27年改定・30年改定の介護保険では、思いっきりやられますね。
医療、福祉は、利益が出る。なぜなら、そのように制度設計されているから。経営者は、ある意味、自分との戦いだと、いつも思うのです。
私は、コンサルティングをしていて、障がい事業をしています。WJUFSの職員さんは、私が出張って来て「利益、利益、利益」と言っていないことを知っています。私は、「適正な利益」を要求しています。
だから、適正な利益は「黒字の平均とベストプラクティスの間くらい。」です。黒字の平均とベストプラクティスが出たら、「当事者」「職員」「地域」「会社」で分けます。悪どく行こうと思えば出来てしまうのでね。
ターゲットを「適正な利益」と決めておけば、私の顔色を窺わずで仕事と向き合えますででしょう?経営者って「太陽と風と雨と土」だし、管理者は「土に種を植えていって、いろんな作物を育てる役目」だものね。
(記事)
サンウェルズの不正請求問題
17万1546件に達した訪問時間のごまかしなどで28億円を不正請求、睡眠センサーの確認だけで30分の訪問看護と申告
サンウェルズは、、、、、報告書では、あまりにも典型的な問題事案であることから、「短時間訪問事案」と「同行者不在訪問事案」という名前まで付けられていた。短時間訪問は17万1546件に及んでいた。
(7月3日のレジメから)
そのために、これからの障害事業に求められることは
1. 福祉の心を体の真ん中に置く。
2. 右手に技術。
3. 左手にそろばん。
4. 全ては、この3つのバランスが大事。
(7月3日のレジメから)
自分たちのやりたい福祉をするのであれば、「適正な利益」を上げること。
適正な利益を上げることは、決して「悪」ではない。
適正な利益を上げたら、4者で分けることが大事。
それは、「当事者」「職員」「地域」「会社」。
適正な利益がなければ、より良いサービスはできない。
適正な利益がなければ、職員の生活向上、能力向上はできない。
適正な利益が無ければ、地域貢献はできない。
利益を特定の人が独占してはならない。
利益の無い事業に将来はない。利益は全てを解決する。