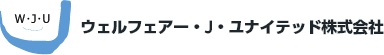今日は、愛媛県経営協の研修です。私と障がいで赤松さんと就学前で山下さんと3人です。なんか、いつもより多くのお申し込みがあるとのことで頑張りたいです。
国は2025年をターゲットに政策を進めてきた(地域包括ケアシステム)。
今年からポスト2025に関わる政策の立案を進めている。ポスト2025は、2040年の社会モデルを求め、多くの 議論、研究会、モデル法人の設定が行われている。
今年、厚労省老健局は、2つの研究会を立ち上げて取りまとめを行った。
- 2040年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会
- 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会
そして今、社会保障審議会介護保険部会で「2040年に向けた政策」への議論が始まっている。
国の政策から、医療事業者と福祉事業者の経営環境が急激に変わろうとしている。
さらに、経営環境の変化は政策だけではなく「社会」「市場」からも同時に起きている。
一部の地域では、関ヶ原の戦いが終わり「寡占化」が始まっている。
そしてまた、一部の地域では、これから関ヶ原の戦いが始まる。
さらには、都市部では、社会福祉法人と株式会社の間で下克上が起きる。
1970年モデル法人と2025年・2040年モデル法人の間でも下克上が起きる。
それぞれ、残された時間で「戦略」を策定し「戦う体制」を整える必要がある。
国は、「2040年モデル」についての政策を世に出す。
2040年までの戦い方のルールは、今年中に分かる。
地域によっては、「生か死か」になる。
チャンスとピンチが背中合わせのスリリングな20年が始まった。
大きな施設が数多くあり100億円の繰越金があっても2040年を保証するものではない。
今、5億円の売上でも、20年後に30億円の規模にもできる。
何もしたくない(変わらない)社会福祉法人。
そんな隙をついて、株式会社が在宅で埋めていくことになる。
もはや、1970年モデルの社会福祉法人はどう戦っていいのかも分からない。
ただただ、ジリ貧になっていく。
その先に待っているのは合併・統合か廃業。
医療を必要とする人は増加する。要介護(要支援)者は増加する。
障がいサービスを必要とする人は増加する。生活支援を必要とする人は増加する。
「悲観する材料は一つもない。」
時代に合わせて変わることができればチャンス、変われなければピンチ。
「あなたはどっち?」
変わり方は勉強すればいい。
変わりたいなら、計画して実行する。
だから、勉強して勉強して勉強する。
努力して努力して努力する。
まず、今から2040年までの事業設計図を作ろう!