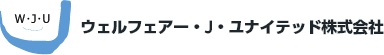参考になれば。
(8月30日のレジメから)
はじめに
ついに、力勝負の時代が来た。強い経営ができない法人は淘汰されていく。
時代が音を立てて変わろうとしている。国は、結果として、全産業において、小規模事業者が消えていく社会を選択したことになる。
やがて、町中華が消え、町の洋食屋さん、町のパン屋さんが消えて行くことになるかもしれない。
(記事を要約)
2025年1~7月に判明した人手不足倒産は全251件。このうち従業員や経営幹部などの退職が直接・間接的に起因した「従業員退職型」は、前年同期比約6割増と急増している。
このペースが続けば、2024年の90件を大幅に上回り、初めて年間100件以上、最悪の場合は2倍に達する見込みだ。
また、今回、十分な給与水準を維持できないことが要因の「賃上げ難倒産」も確認された。A社は、業績悪化に伴い給与を引き下げた結果、従業員の退職が相次ぎ、事業継続が困難となった。
信用調査機関は「賃上げによって優秀な人材を高給で確保する動きが広がるなか、待遇改善をしないことによる人材流出リスクが中小企業を中心に高まっている」と指摘。
「十分な報酬を支払う余力のない中小零細企業の淘汰が、『従業員退職型』倒産として今後表面化する可能性がある」と分析した。
(骨太の方針2025より)
「賃上げこそが成長戦略の要」である。持続的・安定的な物価上昇の下、日本経済全体で1%程度の実質賃金上昇を定着させ、国民の所得と経済全体の生産性を向上させる。
この実現に向け、中小企業・小規模事業者の賃上げを促進するため、適切な価格転嫁や生産性向上、経営基盤を強化する事業承継・M&Aを後押しするなど、賃上げ支援の施策を総動員する。
最低賃金を着実に引き上げ、2020年代に全国平均1,500円という高い目標に向かってたゆまぬ努力を続ける。
将来における賃金・所得の増加にも取り組む。企業の稼ぐ力を継続的に高めるため、GX・DX、スタートアップ、経済安全保障等の分野において、官と民が連携した投資が行われる「投資立国」の取組を進める。
貯蓄から投資への流れを確実なものとし、中長期の視点から国民の資産形成を後押しする「資産運用立国」の取組を進める。
(骨太の方針2025より)
3.人口減少下における持続可能な経済社会の構築
我が国の生産年齢人口は、これからの20年で1,500万人弱、2割以上が減少する。こうした中、かつて人口増加期に作り上げられた経済社会システムを中長期的に持続可能なシステムへと転換することが求められる。
経済・財政・社会保障の持続可能性を確保するためには、生産年齢人口の減少が本格化する中にあっても、中長期的に実質1%を安定的に上回る成長を確保する必要がある。その上で、それよりも更に高い成長の実現を目指す。こうした経済においては、2%の物価安定目標を実現する下で、2040年頃に名目GDP1,000兆円程度の経済が視野に入る。
人口減少が本格化する2030年代以降も、こうした成長を実現するとともに、医療・介護給付費対GDP比の上昇基調に対する改革に取り組み、PBの一定の黒字幅を確保していくことができれば、長期的な経済・財政・社会保障の持続可能性が確保される。
(国税庁の調査書から)
調査によれば、2019年度において所得がマイナス、つまり欠損状態になっている赤字企業は全国に1,812,332社あり、普通法人全体2,767,336社のうち65.49%を占めます。このことから、日本にある企業のうち、約3分の2は赤字企業である。
中小企業・中小法人が多くあっても、税収は増えない。
国は、日本の社会構造の大変革を目指しているのではないかと解される。
国は、全国の法人経営者に新しい価値観を求めている。
給与の上昇から、日本経済を「成長型の新たな経済ステージ」へと移行を狙っている。
国は、必ず、最低賃金を 1,500円にする。
最低賃金を上げることで、日本の会社給与全体を上げることを狙っている。